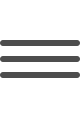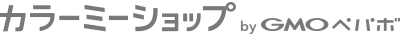土佐和紙ができるまで
楮を育てる→楮蒸しと皮はぎ→原料をつくる→紙を漉く手漉き土佐和紙を漉くのは、本当に大変な工程がかかります。
ここでは、実際にわたしたちTOSAWASHI PRODUCTSが紙漉職人の人々に教わりながら学んできた土佐和紙ができるまでのプロセスをごく簡単に紹介していきます。
※TOSAWASHI PRODUCTSでは、機械漉きと手漉きの土佐和紙を用途に応じて使いわけています。
紙漉き指導=磯崎裕子、森澤真紀、田村寛
取材協力=同上、尾崎あかり、田村亮二、尾崎伸安、浜田治、土佐和紙工芸村
監修=磯崎裕子

楮の栽培
紙漉職人さんたちが、日高村のある谷で、楮を育てています。
それほど大きい畑ではないのですが、もと棚田だったところを借りて育てているそうです。

左は10月に草刈りに出かけたとき、右は12月の暮れの刈り取りのときの風景です。
育て始めて2回目の冬で、ずいぶん葉づきも枝ぶりも旺盛になってきたとか。
楮の刈り取り
楮を刈り取るのは案外難しいのです。しなやかな枝なので、どうにもカマの位置が定まりにくい。
この日刈り取りを指導してくださった尾崎さん(映像に写っている方)曰く、
「最近ののこぎりは刃が細かいのがあるので、
のこぎりで切るのでも枝の切断面がギザギザが少なくてきれいだけど、
のこぎりで切ったものは切断面が凸凹になって水がたまって腐ったりしやすい。
本当はカマでスパッと刈り取った方が
切断面もスパッときれいで腐りにくくて良い」
とのこと。上の映像ではノコギリで切っているシーンが多いのですが、
太いのになるとカマで切るのは本当に難しいんです。
草刈りは、冬場までに月1−2回定期的に行い、芽かきは初夏に行います。
楮はもちろん普通に買うこともできるわけですが、
全国的な課題としてこの楮栽培をする農家が激減しているという課題に直面しています。

(左)刈り取りが終わった楮は束にして揃え、(右)同じ長さに刈り揃えてトラックに積み込みます。
家に持ち帰ったら、お餅などを切る「押し切り」で切り揃えます。
次へ「楮蒸しと皮はぎ」