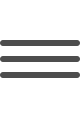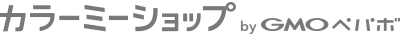土佐和紙ができるまで
楮を育てる→楮蒸しと皮はぎ→原料をつくる→紙を漉く

原料を洗い、煮る。
紙造りは酒づくりとどこか似ているような気がします。
冬場がなんといっても一番仕事の忙しい時期で、冷たい水と付き合い、とにもかくにも重労働です。
左は楮の皮をきれいにはいだ白皮、右はまだちょっと樹皮が残っている黒皮。
かんたんに言えば左は白い紙に、右は黒皮の入った紙になるわけです。
原料は、煮る前に水に漬け、かるく洗ってから大きな釜で煮ます。
原料には、ここまで紹介してきた楮の他にも、三椏や雁皮などがあるわけですが、
それぞれにちょっとずつやり方が違うようです。
煮るときは、ただ単にお湯で煮るのではなく、紙の用途や原料の質に応じて
ソーダ灰や苛性ソーダ、石灰などアルカリ系薬品と一緒に煮込んでいきす。
ソーダ灰や石灰、木灰などはマイルドなアルカリで、白皮のきれいな原料を煮る時に、
苛性ソーダは黒皮の原料やコストを抑えたい紙(薬品で漂白して仕上げる紙など)に用います。

チリトリ
白くてきれいな紙を作る場合、やらなければいけないのがチリトリです。
原料の表面に残ったキズのような部分や、黒っぽい樹皮をひとつひとつ手で取り除いて行くのです。
これが大変。
塩素漂白してしまえばチリトリはいりませんが、
漂白していない方が経年による変色やシミなどが生じにくい紙ができます。
手間を抜こうとすると必ず後で帰ってくる。それが和紙なのです。

たたく!
原料を団子状に小さくまとめて、槌でたたいて繊維をほぐします。
これもまたなかなか面倒・・・
きちんと叩いてやると、水に入れただけでふわっとほぐれてくるから不思議!

左はトロロアオイを叩いているところ。
ツルツル滑るので叩きにくいのですが、このトロロアオイが和紙づくりでは実はカギを握っていたりします。
しかしまるでカニかなんかを叩いてるようであんまり気分のいいものではありません(笑)
右は「タンタン」と原料を叩いてくれる機械です。
手で叩くのは重労働なので、基本的にはこの「タンタン」を使うことが多いそうです。
次へ「紙を漉く」